電動アシスト自転車の開発PJ(2)
「アシスタの実用電費はどの程度か?」
電動アシスト自転車の場合、電力消費は「バッテリーフルチャージで〇〇Km走れます」と一般的に表示され、現在ではワンチャージ=100Kmが商品開発の一つの目標になっているように思われる。一応100Km走れれば、一般的なサイクリングの用途として満足ということなのだろう。
日本では、業界団体である「自転車産業振興協会」が電力消費の試験方法を厳密に規定しており、下図に示すような上り坂、下り坂を含む4Kmの走行を模擬して電力消費を計測することになっている。坂道は7%勾配(4度)に設定されており、実際はこんなに坂道が続くことは稀なので、通常の走行には試験より走行距離が延びる場合が多いと思われる。(カタログにもそのように書いてある)
アシスタ走行距離(カタログ値) 強モード:32Km 0.16Km/Wh
標準モード:38Km 0.19Km/Wh
オートエコモード:54Km 0.27Km/Wh
これらのカタログ値と実走行のデータを比較するため、日ごろよくサイクリングするコースを何回か走行して、平均的な実用電費を計測した。(皇居一周を含む市街地の周回コースで、坂道も結構含まれる。信号による停止も含めて平均速度は約20Km/h)
運転中の消費電力を計測するため、リチウム電池の出力端に電圧・電流計を接続して、消費電力を運転中に観察できるようにした。(中華製の電力計であるがよく出来ている)
下図が8回のチャージの走行データであるが、平均電費として0.246Km/Whというデータが得られた。これはカタログ値の「標準モード」と「オートエコモード」の中間に位置する。(ちなみに走行はすべて「標準モード」でおこなった)
バッテリー残量表示メーターと消費した電力量の関係を下図に示す。180Whで残量はほぼゼロをしめす。また電圧も使用開始時に28.9Vであったものが、24Vまで低下する。(これはリチウムイオン電池の典型的な電圧低下カーブであるが)これらの計測データから、ヤマハ/ブリジストンはリチウムイオン電池の放電カットオフ電圧を1セル当たり約3.4V(=24/7)と高めに設定していることが推定される。これは多分寿命と安全性を考慮したものであろう。定格容量の82%を常用の使用範囲としていることになる。(180/219=0.82)今回の計測値から割り出された180Whという常用使用範囲は、多分に経年劣化も含まれているので、新品の時は200Wh程度であった可能性もある。カットオフ電圧も本当は3~3.2Vぐらいが適当と思うが、メーカが公表していないので真相は不明。
今回、電流・電圧計をつけて走行した結果、電動アシスト自転車の電力消費の挙動が良く判って面白かった。電力を消費するのは殆ど始動から定常速度に至る加速時と坂道の時だけで、定常速度で巡行するときは50~80Wほどしか消費していない。(当然のことであるが)また定常速度でも電力消費を最小にするギヤ比が存在することも分かった。ギヤ比を上手く選べばモータの回転数を効率が良い範囲にコントロールすることが可能である。これは将来モータを設計する時に考慮すべき重要なことである。変速機は7段(11・13・15・18・21・24・28/チェーンリング41歯)としているが、実際は東京都内の急坂でも3速(21)で済んでいる。また巡行速度でも5速(15)が一番電力消費が少ない。つまり中央の3段で変速はすべてカバーされることになる。(電動アシストの威力である)
現在使用しているアシスタの重量は実測22.5Kgであり、オリジナルより多少軽量化しているが、今回の開発の目標としている10Kgには程遠い状況である。ベースがママチャリなので車体が重いのは仕方がないとして、パワーユニットとバッテリーの重量が5.5Kgもあるのは救いがたい。超高級なバイクでは5Kgを切るものもあるので、これを電動化すれば10Kgに収めることも可能であるが、いかにもバランスが悪い。片やグラム単位で繊細に勝負するバイクに、オートバイの部品なみに武骨なパワーユニットを乗せるのは無粋以外の何物でもない。ベースとなるバイクとパワーユニット、バッテリーの重量配分をどうするか、設計者の工学的センスが問われる。(次回に続く)






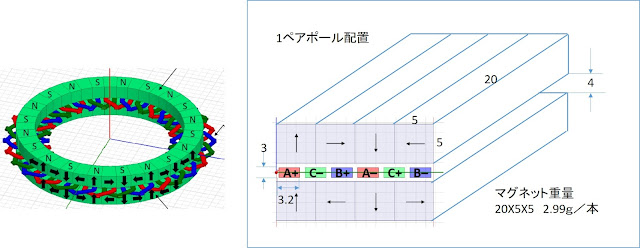


コメント
コメントを投稿