電動アシスト自転車の開発PJ(8)
「ミッドシップ型パワーユニットの構想」
前回パワーユニットおよびモータの型式について3ケースの検討をやって行くとしていたが、今回は最初に「ミッドシップ型パワーユニット」について、基本的な構想をまとめた。
1)DCモータの選定
一番肝心のモータについては、24/36V、250Wクラスの市販のDCモータを種々調査した。航空機模型用、ドロ-ン用のモータも候補に上がったが、最終的に、マブチが最近市販を始めたブラシレスDCモータ(IS-94BZC)が電動アシスト用モータとしてはベストフィットとの結論を得た。
IS-94BZCの主要諸元 電圧24V; 定格トルク;1.1Nm@2250rpm(260W)
ピークトルク;2.0Nm@1950rpm(410W)
電圧36V; 定格トルク;1.0Nm@3600rpm(380W)
ピークトルク;2.0Nm@3250rpm(680W)
ディメンジョン; 直径X厚さ=80㎜X45.5㎜ 重量=830g
このモータは外観からアウターロータ方式と思われるが、トルク特性が太く、電動アシスト専用に開発されたモータと比較しても、遜色ない性能を持っていると思われる。(各メーカのモータ単独仕様は発表されていないので、推測であるが)重量も単体で1.0Kgを切っており優秀である。また防塵仕様になっているので、自転車にそのまま装着できる点も魅力である。 このシリーズには少し小ぶりのIS-92BZC(厚さが7㎜薄く、重量は650g)もあるが定格トルクが0.65Nmと小さいので、今回はIS-94BZCの方をメインに検討を進める。(最後に重量と厚さをシビアに削る必要がでた場合は再検討の可能性もある)
このモータは、例えばモノタロウ等の通販で購入可能であり、価格も3万円以下と手ごろである。
2)遊星ギヤの選定
サーボモータ用に色々な遊星ギヤが市販されているが、減速比10前後(7~13)で、2Nmの入力トルクを伝達し、且つ軸方向長さをミニマムとする遊星ギヤとなると、選択範囲はかなり狭まる。最終的にマテックス社のLGU75-7MLDを選択した。この遊星ギヤはギヤ単体での販売なので、入力軸、出力軸、およびギヤケースは購入者が用意する必要がある。入出力軸はインボリュートセレーションと特殊なはめ合いなので、市販の部品は使えず、特注加工が必要となる。騒音が大きそうな構造である点が気になる。
LGU75-7MLDの主要諸元; 減速比; 1:7 最大伝達トルク(出力側);17.65Nm
ディメンジョン;直径X厚さ=75㎜X22.6㎜ 重量=265g
3)フリーホイールの選択
モータ、遊星ギヤの出力はドライブスプロケットを通じてチェーンに伝達されるが、スプロケットと出力軸にはラチェット機能が必要である。これには自転車で一般に使われているフリーホイールを使うこととした。出来るだけ小さな歯数を採用したいが、一般的に市販されているのは16歯が最小である。初期検討ではシマノのSF1200シリーズの16歯を採用することにした。(海外の海賊メーカからは14歯のものも売られているが、先ずは信頼性重視でシマノで検討を進める)・・・どうしても少ない歯数が必要な場合は、椿本のカム&ローラクラッチ等を使って加工するケースもあり得る。
4)全体構成
パワーユニットを構成する主要部品を下図に示す。これらは何れも入手可能な市販の製品である。主要部品の合計重量は1245gとなった。
5)パワーユニットの許容幅(長さ)について
パワーユニットをボトムブラケットの下部に取り付け、先端のスプロケットでチェーンを駆動する一軸構造とする場合、クランクに干渉しないように、パワーユニットの全長は105mm+10mm以内に抑える必要がある。(今回ベース車であるCannondaleのSynapseはBB30のボトムブラケット装備車であり、Qファクターはロードで標準的な150㎜となっているので結構狭い。)
6)パワーユニットの構成
選択した部品を使って、パワーユニットの構成図を作成した。作図上は全長105㎜以内に納まりそうである。遊星ギヤとモータの接続カップリング、出力軸(シャフト)、ケースは自作の必要があるが、いずれも専門の機械加工メーカに頼めば作れる部品である。(やや難易度は高いが)パワーユニットの重量はこの時点で約1.5Kgとなってしまった。
7)パワーユニットのトルク特性
パワーユニットのトルク特性を計算した。入手可能な部品で構成するケースⒶ(減速比21.875)と理想的に減速比1:9の遊星ギヤと14歯のフリーホイールが可能になったケースⒷ(減速比32.14)の2ケースについてトルク特性を示す。ケースⒶはクランク軸トルクが40Nm前後とSpecialized社並みである。ケースⒷでは60Nmと大多数の市販ユニットのレベルに到達する。
現状はBB30標準のQファクター=150㎜のままであるが、例えばボトムブラケットに MTB用の幅広タイプを採用すれば、Qファクターは170㎜程度まで広げることが出来る。プラス20㎜の余裕が出来れば、市販の減速ユニット(例えばエイブルのVRB-042C・・・減速機部分の外径が42㎜と細身である、重量=約600g)が採用出来るようになり、工作が楽になる。(ボトムブラケット拡張の困難さとの取り合いであるが)
②ドライブスプロケットのかかり方向
現状はモータの直径の問題から、通常とは逆のかかり方になっているが、上記でクランクの幅が広げられてたら、市販の細身の減速ユニットが採用でき、ママチャリタイプのかかりも可能となる。この点も今後の検討課題である。チェーン合力方式により人力+モータの過大トルクがナローチェーンにかかるが、プロの選手の馬力(1KWを超える)にも耐えていることから、この点は問題なしと判断した。
③コントローラー/ドライバー
マブチはこのモータ専用のコントローラー/ドライバーを用意しているが、これについては例えばヤマハPAS用の制御装置、マイコン一式をそのまま流用することを考えている。これは東芝のTMPM370マイコンを使ったもので、ベクトル制御、トルク制御など電動アシスト用モータに必要な機能が一式組み込まれており、作業が簡単である。(モータを繋ぎ変えるだけで済む。車速信号、クランクトルクの入力信号は繋ぎ込む必要があるが、トルク信号に関してはクランクにパワーメータ等を取り付けて取り込む等の工夫が必要となる。)
④感想
モータの車体へのアダプター、またアイドルギヤは新しく設計する必要があり、これらは上記で見積もった重量に対して追加の重量となる。メーカのパワーユニットがボトムブラケット部の重量込であることを考慮すると、Specialized社の SL1.1Motorの1.95Kgが如何に軽いかが判る。ミッドシップ型パワーユニットでは、メーカが英知を集めて最適設計しており、樹脂ギヤ、マグネシウムのケースなど高価な材料をふんだんに使っていることから、同じ土俵で戦ったらとても敵わないというのが、今回の検討での実感である。ただし、今回検討した方式は普通の自転車に後付けできて、トルク特性、重量ともメーカのものに肉薄できる点に大きなメリットがある。また全体重量も10Kgに限りなく近づけることができるポテンシャルを持っている。これはマブチモータの性能がいかに優れているかということだ。
(次回に続く)






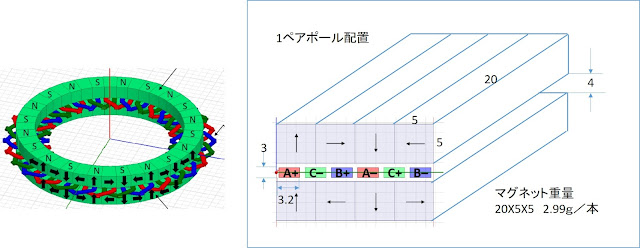


コメント
コメントを投稿